自民党といえば「派閥政治」。
総裁選や人事、政策決定にまで大きな影響を与えてきた仕組みです。
しかし、時代とともに派閥の力は弱まりつつあります。
それでも「人脈政治」は今も残り続けています。
本記事では、自民党における派閥の歴史と役割、そして現代の変化について解説します。
なぜ「自民党=派閥政治」と言われるのか

自民党が1955年に結党されて以来、派閥政治は日本政治の最も特徴的なシステムとして機能してきました。
この仕組みが生まれた背景には、自民党の特殊な成り立ちがあります。
自民党は保守合同により、自由党と日本民主党が統合して誕生しました。
しかし、この統合は理念的な一致ではなく、社会党の勢力拡大に対抗するための政治的な必要性から生まれたものでした。
そのため、党内には異なる政治的系譜を持つグループが並存することになったのです。
1955年以降、自民党は「55年体制」と呼ばれる長期政権を築きました。
野党が分裂し、政権交代の可能性が低い状況の中で、実質的な権力闘争は自民党内部で行われるようになりました。
派閥は、この党内権力闘争の主要な舞台となったのです。
派閥の最も重要な機能は「総理大臣を決める仕組み」でした。
総裁選において、各派閥は組織票を持ち、その支持を得ることが総裁への道筋となりました。
国民の支持よりも、まずは党内の派閥間の力学が首相の座を左右したのです。
また、派閥は政治資金と人材を集める組織的な役割も果たしました。
派閥の長は企業や団体から資金を調達し、それを所属議員に分配しました。
選挙での支援、政策立案のサポート、官僚との人脈形成など、政治家として必要な資源を派閥が提供する構造が確立されました。
歴史的な派閥の役割
田中派(田中角栄)
自民党派閥政治の象徴的存在が田中角栄率いる田中派でした。
田中は「数の力」を重視し、積極的な資金調達と人材登用により、1970年代から1980年代にかけて党内最大派閥を形成しました。
田中派の特徴は、徹底した実利主義でした。
「日本列島改造論」に代表される大型公共事業を通じて、建設業界や地方自治体との強固なネットワークを構築しました。
政治資金は潤沢に流れ、所属議員の選挙や政治活動を手厚くサポートしました。
田中は「コンピューター付きブルドーザー」と呼ばれ、全国の選挙区情勢を詳細に把握していました。
このデータに基づいた戦略的な選挙支援により、多くの議員が田中派の恩恵を受けました。
1972年には総理大臣に就任し、派閥の力が国政を動かす構図を鮮明にしました。
しかし、1976年のロッキード事件により田中は失脚します。
それでも田中派の組織力は健在で、後継の竹下登、金丸信らが派閥を継承し、長期間にわたって自民党政治の中核を担い続けました。
福田派(福田赳夫)
田中派に対抗する保守本流として位置づけられたのが福田赳夫率いる福田派でした。
福田は大蔵官僚出身で、「クリーンな政治」と財政規律を重視する政策路線を掲げました。
福田派は田中派の金権政治とは対照的に、政策論議を重視する知的な派閥として自らを位置づけました。
しかし、現実の政治においては、田中派の豊富な資金力と組織力に対抗するため、独自の資金調達ルートを確保する必要がありました。
1970年代後半の「角福戦争」と呼ばれる総裁選争いは、派閥政治の典型例でした。
田中の「数の論理」と福田の「正統性の論理」が激突し、最終的には両者とも総裁の座を逃し、大平正芳が漁夫の利を得る結果となりました。
この抗争は、派閥間の対立が政策論争を超えた権力闘争であることを浮き彫りにしました。
同時に、派閥の領袖の意向が党全体の方向性を大きく左右する構造を明確に示しました。
中曽根派や竹下派
1980年代に入ると、竹下登の「経世会」(旧田中派)が金権政治の象徴的存在となりました。
竹下派は田中派の組織と資金力を継承し、さらに洗練されたシステムを構築しました。
経世会の特徴は、主要ポストを体系的に分け合う「分配の政治」でした。
派閥の規模と影響力に応じて、閣僚ポスト、党役職、各種委員会の委員長職などが配分されました。
この仕組みにより、各派閥は一定の権力を保持し、党内の安定が保たれました。
中曽根康弘も独自の派閥を形成し、「戦後政治の総決算」を掲げて改革派としての地位を築きました。
中曽根派は比較的小さな派閥でしたが、他派閥との連携により政権を獲得し、5年間の長期政権を実現しました。
この時代の派閥政治は高度に組織化され、「派閥均衡人事」が常態化しました。
総理大臣は各派閥の利害を調整し、バランスの取れた人事を行うことが求められました。
これにより政治的安定は保たれましたが、同時に改革への機動性は失われる側面もありました。
総裁選と派閥の力学
自民党総裁選における派閥の役割は、日本政治の最も特徴的な仕組みの一つでした。
「派閥の数=総裁選の得票力」という単純な構図が長期間続いたのです。
総裁選の投票権を持つのは党所属の国会議員です。
各派閥の領袖は、総裁選に向けて所属議員の投票行動を統制しました。
議員個人の政策的信念や個人的好みよりも、派閥の意向が投票を決定する要因となりました。
派閥の領袖が候補者を決め、支持を取り付ける仕組みは高度に発達していました。
複数回の投票が行われる場合、第一回投票で下位となった候補の支持派閥がどこに票を流すかが勝敗を決しました。
この過程で、政策的な約束や人事での処遇などが取引材料として使われました。
最も象徴的だったのは、国民人気より「派閥の談合」で首相が決まる時代が長く続いたことです。世論調査で高い支持を得ている政治家でも、派閥の支持を得られなければ総裁になることはできませんでした。
逆に、国民的知名度は低くても、派閥間の調整により総裁に就任するケースも見られました。
この仕組みは、政治的安定をもたらす一方で、民主主義の観点から問題も指摘されました。
有権者の意向が直接反映されない総裁選出システムは、「密室政治」として批判されることも多くありました。
| 派閥名(正式名称) | 通称 | 主な領袖・出身首相 | 所属議員数(目安) | 特徴・影響力 |
|---|---|---|---|---|
| 清和政策研究会 | 安倍派 | 安倍晋三、福田康夫、森喜朗 | 約90人前後 | 保守色が強く、安全保障や改憲に積極的。最大派閥だが安倍氏亡き後、求心力低下。 |
| 志帥会 | 二階派 | 二階俊博 | 約40人 | 中国とのパイプ、地方組織に強い。二階氏の影響力は衰退傾向。 |
| 宏池会 | 岸田派 | 岸田文雄、大平正芳、宮澤喜一 | 約45人 | ハト派・穏健保守。外交で対話重視。岸田首相の基盤。 |
| 水月会 | 石破派 | 石破茂 | 約15人 | 地方に人気。防衛や農業政策に強み。党内では孤立気味。 |
| 志公会 | 麻生派 | 麻生太郎 | 約55人 | 経済政策や財務省との連携が強み。実務派集団。 |
| 平成研究会 | 茂木派(旧竹下派) | 竹下登、橋本龍太郎、茂木敏充 | 約50人 | 政策通が多く、実務に強い。首相候補を複数輩出。 |
| 無派閥議員 | – | 小泉純一郎、菅義偉など | 約60人 | 国民的人気を背景に派閥に頼らず首相になるケースも。 |
現代の派閥解体と再編
派閥政治の転換点となったのは、2001年に発足した小泉純一郎政権でした。
小泉首相は「自民党をぶっ壊す」と宣言し、従来の派閥政治からの脱却を図りました。
小泉政権以降、派閥の影響力は明らかに弱体化しました。
総裁選において国民人気が重視されるようになり、世論調査の支持率が大きな要因となりました。また、党員・党友による予備選挙の導入により、国会議員票だけでは総裁を決められない仕組みも取り入れられました。
2006年から2020年まで長期政権を担った安倍晋三首相の時代には、清和会(安倍派)が影響力を大幅に拡大しました。
しかし、これは従来型の派閥政治の復活ではなく、安倍個人のリーダーシップに基づく新しい形の権力構造でした。
安倍政権下では、「官邸主導」が徹底され、重要な政策決定は首相官邸で行われました。
各省庁の人事も官邸が握り、派閥や族議員の影響力は大幅に削がれました。
この変化により、政策決定プロセスはより迅速になりましたが、同時に権力の集中に対する懸念も生まれました。
2021年以降、自民党では相次ぐ政治資金問題により派閥の解散や休止が続いています。
2023年には「政治資金パーティー」をめぐる裏金問題が発覚し、安倍派(清和政策研究会)をはじめ複数の派閥が解散を余儀なくされました。
これらの動きは、表面的には派閥政治の終焉を意味するように見えます。
しかし、政治の現実はより複雑です。
公式な派閥組織は解体されても、政治家同士の人脈やネットワークは簡単には消えません。
現在公に残っている派閥は、麻生派だけだと言われています。
まとめ|派閥が弱まっても残る「人脈政治」
現代の自民党では、表向きの派閥解体が進んでいますが、「つながり」そのものは完全には消えていません。
政治家たちは依然として、政治資金、選挙支援、情報収集、政策立案などで相互に依存し合っています。
政治家は支援者、同僚議員、官僚とのネットワークを重視し続けています。
これらの関係は、従来の派閥とは異なる形で機能していますが、本質的には同様の役割を果たしています。
政策グループ、勉強会、同期会など、新しい形の結びつきが生まれています。
また、選挙制度の特性上、政治家は地元の支援者や利益団体との関係を維持する必要があります。
これらの関係は、派閥解体後も重要な政治的資源として機能し続けています。
形は変わっても「派閥的な力学」は今後も続くと考えられます。
人事や政策決定における水面下での調整、利益配分のメカニズム、権力バランスの維持などは、組織の名称や形態が変わっても、政治の基本的な機能として残り続けるでしょう。
重要なのは、これらの変化が日本の民主政治にどのような影響を与えるかです。
派閥政治の弱体化により、政治がより透明で国民に開かれたものになる可能性がある一方で、新しい形の利益調整メカニズムが必要になるかもしれません。
自民党の派閥政治は、戦後日本政治の重要な特徴でした。
その変容は、日本の政治システム全体の変化を象徴しています。今後も、形を変えながら継続する人脈政治の動向を注視していく必要があるでしょう。

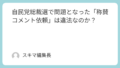
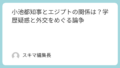
コメント