国産ブランド保護と産地反発、その狭間で揺れる農水省の政策
ロイターのニュースが今話題となっています。
小泉進次郎が大臣を務める農林水産省が高級ブドウ「シャインマスカット」の栽培権(ライセンス)をニュージーランドに供与する方向で検討していることがわかりました。
もし実現すれば、日本の果樹品種で初めてのライセンス供与となります。
このニュースについて、詳しくお伝えします。
ニュースの概要

農林水産省が、日本で開発された高級ブドウ「シャインマスカット」の栽培権(ライセンス)をニュージーランドの企業に供与する方向で検討していることが明らかになった。
正式に日本政府が海外へ栽培ライセンスを与えるのは初めてとなる可能性がある。
背景には、日本産の果樹品種が海外に流出し、無秩序に栽培されている現状がある。
ただし、国内の生産者団体や山梨県などの産地からは
「国産輸出が進まない中で海外にライセンスを出せば国内農家が不利になる」
と強い反発が出ている。
背景:日本ブランドを守る「攻めの農政」
日本は果樹品種の開発力において世界的に評価が高い。
シャインマスカットは1980年代後半から30年近い歳月をかけて農研機構が育成し、2006年に品種登録された。
糖度が高く種がなく、皮ごと食べられる手軽さで人気を集め、国内では高級フルーツの代名詞ともいえる存在となった。
しかしその人気ゆえに、種苗が海外に持ち出され、韓国や中国などで無断栽培される事態が広がった。
現在では東南アジア市場に「中国産シャインマスカット」が出回っており、日本ブランドが侵食されている。
農水省はこの損失を年間100億円以上と試算している。
そこで政府は、今年4月に改訂した
「食料・農業・農村基本計画」に
「有望な果樹品種を戦略的に海外へライセンス供与する」方針を明記。
無秩序な流出ではなく、公式な契約に基づき監視や品質保証を行い、世界市場を押さえる狙いを掲げてきた。
今回のニュージーランドへの供与検討は、その第1号案件にあたる。
争点:なぜ産地が反発するのか
表面的には「ブランド保護」「違法流出防止」という正論に見える政策だが、現場の生産者にとっては大きな懸念がある。
最大の問題は、日本産シャインマスカットの輸出が思うように進んでいないことだ。
植物検疫や輸送コストの高さが壁となり、多くの産地は海外市場に直接アクセスできない状況にある。
つまり、
「自分たちは輸出できないのに、ニュージーランドでライセンス栽培されたシャインマスカットが世界市場に出回る」
ことになれば、競争条件が不公平だという不満が生まれる。
実際、25日には山梨県の長崎幸太郎知事が国会内で小泉進次郎農林水産相に抗議し、
「輸出ができない中でライセンスが供与されれば、生産者が大きな打撃を受ける」と直訴した。
小泉氏は
「産地の理解が得られない中では今後の海外許諾は進めない」
と応じたとされるが、政策推進と産地調整の難しさが浮き彫りになった。
生活への影響:私たちに関係あるのか?

一般消費者にとっても、この問題は決して他人事ではない。
まず考えられるのは価格の変動だ。
もしニュージーランド産のシャインマスカットが輸入されれば、国内市場で価格競争が起きる可能性がある。
これまで「高級フルーツ」として贈答用や特別な嗜好品の位置づけだったシャインマスカットが、より手頃な価格でスーパーに並ぶ日が来るかもしれない。
一方で、日本産の農家にとっては深刻な打撃となり得る。
高いコストをかけてブランドを維持してきた国内産地が、低価格な輸入品との競争にさらされれば経営が揺らぐ。
結果として、地域農業の衰退や雇用の減少につながる懸念もある。
さらに「贈答文化」にも影響が及ぶ可能性がある。
お中元やお歳暮で「国産シャインマスカット」を選ぶ意味は、ブランド価値に支えられてきた。
だが輸入品が増えれば、そのプレミアム感が失われるかもしれない。
価格を取るのか、品質&農家を守るかを選ぶ必要があるのかもしれない。
ネットやSNSの反応
X(旧Twitter)などのSNSでは、フィフィが投稿したことにより、
このニュースに対してさまざまな意見が飛び交っている。
⬜️シャインマスカット栽培権、農水省がNZへ供与検討 小泉氏に山梨県抗議https://t.co/fRYCWYKCYx
— フィフィ (@FIFI_Egypt) September 25, 2025
おいおい小泉進次郎農林水産大臣さん、何なってんの…
- 「なぜまず輸出支援をしないのか。順序が逆だ」
- 「日本のブランドを守るどころか、自ら価値を下げている」
- 「また農家の声を置き去りにした官僚主導の政策だ」
といった批判が目立つ。
一方で、肯定的な声も一部にはある。
- 「無秩序に栽培されるよりは、ライセンスを与えて監視したほうがマシ」
- 「ニュージーランドと組めば周年供給が可能になり、世界市場でのシェア拡大につながる」
と、グローバル市場戦略として評価する見方もある。
今後の展望:政策は修正されるのか
小泉農相は「産地の理解が得られない中で進めることはない」と述べたが、
農水省はニュージーランド企業からの相談を受けて検討を進めてきた経緯を認めている。
つまり、「完全撤回」ではなく「説明と調整を行う」というスタンスに見える。
今後は、
①国産シャインマスカットの輸出体制整備
②産地への利益還元スキーム
③ライセンス先市場との棲み分け
が政策実現のカギになるだろう。
もし日本が「輸出後進国」のままであれば、海外に市場を奪われ続けることになる。
逆に輸出体制が整い、ライセンス供与と輸出を組み合わせて世界戦略を描ければ、日本の果樹ブランドは守られる可能性もある。
筆者のまとめ・意見
今回のニュースは「攻めの農政」と「現場の不安」が正面衝突した典型例だと思う。
国としては違法流出を防ぎ、グローバル市場で主導権を握りたい。
一方で農家にとっては「まず自分たちが輸出できる環境を整えてからにしてほしい」という切実な声がある。
個人的には、ライセンス供与自体は長期的に見て日本ブランドを守る有効策だと考える。
しかしその前提は、国内生産者が正々堂々と輸出競争に参加できる体制が整っていることだ。
輸送・検疫の課題を放置したまま海外に門戸を開くのは、拙速であり逆効果になりかねない。
「世界に誇る品種をどう守り、どう広めるか」
その問いに答えを出すことが、日本農業の未来を決定づけるだろう。

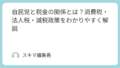
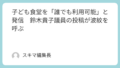
コメント