維新と連立を組むことで誕生した高市新総理。
連立合意書の中に、「医療法に関する三党合意書」というものがありました。
これは、自民、公明、維新の3党によってまとめられた医療制度の根幹部の改正内容が定められたものです。
今回はそんな「医療法に関する三党合意書」についてご紹介します。
なぜ「医療法の三党合意」が注目されているのか
2025年、与野党の間で交わされた「医療法に関する三党合意書」が大きな注目を集めています。
この合意は、自民党・公明党・日本維新の会の3党によって取りまとめられたもので、医療制度の根幹である「医療法」の改正に向けた基本方針を定めたものです。
背景には、少子高齢化や地域医療の崩壊といった長年の課題があります。
とくに地方では医師不足が深刻化しており、「このままでは医療が受けられない地域が増えるのではないか」という不安が広がっていました。
このような中で、政治的な立場を超えて「持続可能な医療体制の構築」を目指すという三党の合意は、国民にとっても大きな意味を持つ動きといえます。
維新と連立合意書の中にも
「医療法に関する三党合意書」及び「骨太方針に関する三党合意書」令和七年度中に実現」と書かれています。
医療法に関する三党合意書の概要
合意書は、政府与党の自民党と公明党、そして野党の日本維新の会の3党によって交わされました。主な合意内容は以下の通りです。
- 地域医療構想の再検討と実効性の強化
- 医師の偏在解消に向けた制度的支援
- 医療機関の再編・統合を支える国の支援策
- 医療DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進
合意の根底には、
「国民がどこに住んでいても、必要なときに適切な医療を受けられる社会を実現する」
という理念があります。
単なる法改正ではなく、今後10年を見据えた医療のあり方を再構築するための政治的な合意といえるでしょう。
維新が求める内容は、
令和7年2月20日に「社会保険料を下げる改革案(たたき台)」を公表し、
国民医療費の総額を、年間で最低4兆円削減することによって、
現役世代一人当たりの社会保険料負担を年間6万円引き下げるとされていることを目標としています。
なぜ今、医療法改正なのか?
医療法は、医療提供体制の基盤を定める重要な法律です。
しかし、現在の制度は人口が増え続けた時代の仕組みを前提にしており、少子高齢化や地域格差が進む現代の状況に十分対応できていません。
とくに問題となっているのが次の4点です。
- 医師不足と都市部への偏在
地方や離島では医師の確保が難しく、救急医療や産科などの診療科が縮小。 - 医療機関の老朽化と経営難
中小病院では経営の持続が困難になり、再編や統合の必要性が高まっています。 - 高齢化による医療需要の急増
慢性疾患や介護と医療の連携が不可欠な時代に。 - コロナ禍で明らかになった脆弱性
病床確保やデータ共有の遅れが、パンデミック対応を難しくしました。
こうした課題を踏まえ、三党合意は「今の医療法を時代に合った形に更新する」ことを目的にしています。
合意のポイントとその狙い
【ポイント1】地域医療の再構築
地方の医療機関を支えるため、国と自治体が一体となった地域医療計画を策定。
大病院だけでなく、診療所・介護施設との連携を強化し、地域全体で患者を支える体制を整えます。
【ポイント2】医師の働き方改革
長時間労働が常態化している医師の勤務環境を改善するため、勤務医の労働時間の上限設定や支援金制度を導入。
医療の質を守りながら、医師が安心して働ける環境づくりを目指します。
【ポイント3】医療DXの推進
電子カルテの標準化、遠隔診療の普及、マイナンバーとの連携による医療情報の一元化など、デジタル化を本格的に進めます。
これにより、患者がどの病院に行っても自分の医療情報を共有できるようになり、効率的で安全な診療が可能になります。
【ポイント4】国と地方の協力体制強化
医療は地域差が大きいため、国が一方的に制度を決めるのではなく、地方自治体の実情を踏まえた「共同行政」を推進。
各地域での柔軟な医療計画の運用を認め、地域医療の持続性を高めます。
「骨太方針」との違い
混同されやすいのが「骨太方針」に関する三党合意との違いです。
「骨太方針」は、政府が毎年策定する経済財政運営の全体方針であり、医療だけでなく教育・福祉・防衛など幅広い分野を包括しています。
一方、「医療法に関する三党合意書」は医療制度に特化した具体的合意です。
骨太方針の中で示された医療改革の方向性を、実際の法改正として具体化するためのものといえます。
今後のスケジュールと課題
三党合意を受けて、政府は2026年度までに医療法改正案を国会に提出する予定です。
主なスケジュールは以下のように想定されています。
- 2025年度内:改正案の最終調整・国会提出
- 2026年度:改正医療法の施行・地方計画の策定開始
- 2027年度以降:全国で地域医療構想の再構築を本格始動
ただし、課題も少なくありません。
- 地方の財政力による格差
- 医療人材確保の難しさ
- 医療DX推進に伴うセキュリティリスク
- 民間医療機関の合意形成の遅れ
これらの課題を解決しなければ、制度改革が「絵に描いた餅」となりかねません。
維新との連立合意書内でも2025年に具体的な制度設計を実現すると書かれています。
国民にとっての影響とは
今回の三党合意は、国民の医療のあり方に直結する重要な転換点です。
- 地方でも高度医療を受けやすくなる
- 遠隔診療の普及で通院負担が減る
- 医療情報の共有で重複検査などが減少
といったポジティブな側面があり効果が期待されます。
一方で、
- 医療機関の再編による病院統合
- 診療報酬制度の見直しによる影響
- 財源確保に伴う国民負担の増加
といった懸念も残ります。
制度の運用次第で、国民生活への影響は大きく変わるため、今後の政策動向を注視する必要があります。
まとめ
医療法に関する三党合意書は、「医療の持続可能性」という大きなテーマに政治が真正面から取り組んだ結果といえます。
自民党・公明党・日本維新の会という異なる立場の政党が一致して合意したことは、医療制度改革に対する国の本気度を示すものです。
医療は誰にとっても身近で、そして不可欠な社会インフラです。
今後の法改正が、都市と地方、若者と高齢者、すべての世代にとって「安心できる医療」を実現するものになるかどうか——その成否が問われています。

https://o-ishin.jp/news/2025/images/1818_001.pdf
https://ajhc.or.jp/siryo/20250606_3g.pdf

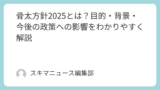
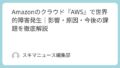
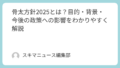
コメント