戦後の日本は「奇跡の経済成長」と呼ばれる急成長を遂げました。
その中心にいたのが自民党です。
池田勇人の「所得倍増計画」から小泉純一郎の「構造改革」、安倍晋三の「アベノミクス」まで、自民党は経済政策を通じて日本の成長と安定を支えてきました。
本記事では、自民党と経済成長の関係を時代ごとに解説します。
高度経済成長と自民党

池田勇人の「所得倍増計画」
1960年、池田勇人首相は「所得倍増計画」を発表しました。
この計画は10年間で国民所得を2倍にするという野心的な目標を掲げ、日本の高度経済成長の象徴的政策となりました。
池田政権は「寛容と忍耐」をスローガンに、経済成長を最優先とする政策運営を行いました。
具体的には、設備投資の促進、技術革新の推進、輸出産業の育成に重点を置きました。
政府は大規模なインフラ整備を進め、東海道新幹線の建設や高速道路網の整備など、経済成長の基盤となる社会資本の充実を図りました。
この政策は見事に成功し、実際には7年で国民所得は2倍に達しました。
1960年代の日本の実質経済成長率は年平均約10%という驚異的な数字を記録し、「東洋の奇跡」と世界から注目されました。
田中角栄の「日本列島改造論」
1972年、田中角栄首相は「日本列島改造論」を提唱しました。
この政策は、太平洋ベルト地帯に集中していた産業を全国に分散させ、地方の活性化と国土の均衡ある発展を目指すものでした。
田中政権は大規模な公共事業を通じて地方経済の振興を図りました。
新幹線網の全国展開、高速道路の建設、工業団地の造成など、インフラ投資を積極的に推進しました。
この政策により、地方にも製造業が根付き、地域間格差の縮小に一定の効果をもたらしました。
しかし、この大規模な財政出動は後に「土建国家」と呼ばれる構造を生み出し、公共事業への依存体質を強化することにもなりました。
また、急激な開発により環境問題や地価高騰といった副作用も生じました。
経済大国としての地位確立
1968年、日本のGNP(国民総生産)は西ドイツを抜いて自由主義諸国第2位となり、名実ともに経済大国としての地位を確立しました。
自民党の経済重視政策により、日本は戦後復興から高度成長を経て、わずか20年余りで世界有数の経済大国へと変貌を遂げました。
この時期の自民党政権は、企業の設備投資を促進する税制優遇措置、輸出振興策、産業政策などを通じて、民間企業の活力を最大限に引き出すことに成功しました。
また、終身雇用制度や企業内労働組合といった日本型雇用システムとも調和し、労使協調による安定した成長基盤を築きました。
バブル崩壊と「失われた30年」
バブル経済の発生と崩壊
1985年のプラザ合意後、急速な円高に対応するため、政府と日銀は大幅な金融緩和政策を実施しました。
この低金利政策により、株価と地価が異常な高騰を見せ、いわゆる「バブル経済」が発生しました。
竹下登首相時代の1989年、日経平均株価は3万8915円の史上最高値を記録しました。
しかし、1990年代初頭からバブルは崩壊し、株価と地価は暴落しました。
多くの金融機関が不良債権を抱え、企業の設備投資は激減し、日本経済は長期低迷期に突入しました。
自民党政権は当初、景気刺激策として大規模な公共事業を実施しましたが、効果は限定的でした。むしろ財政赤字が急拡大し、国債残高が増加する結果となりました。
橋本内閣の金融ビッグバンと規制緩和
1996年、橋本龍太郎首相は「金融ビッグバン」を打ち出し、金融制度の大幅な規制緩和と自由化を推進しました。
従来の護送船団方式から競争原理に基づく金融システムへの転換を図りました。
具体的には、銀行・証券・保険の業務の垣根を取り払う金融制度改革、外国為替法の改正による資本取引の自由化、手数料の自由化などが実施されました。
これらの改革は日本の金融システムの国際競争力向上を目指したものでした。
しかし、この時期の規制緩和は不良債権問題の根本的解決には至らず、むしろ金融機関の経営不安を増大させる側面もありました。
1997年には山一證券や北海道拓殖銀行が破綻し、金融システム全体への不安が高まりました。
景気低迷と国民の不満
1990年代から2000年代にかけて、
日本経済は「失われた10年」「失われた20年」と呼ばれる長期停滞に陥りました。
実質GDP成長率は1%前後にとどまり、デフレが常態化しました。
この間、自民党政権は景気対策として総額100兆円を超える経済対策を実施しましたが、根本的な経済活性化には結びつきませんでした。
公共事業による景気刺激策の効果は次第に減少し、財政赤字だけが拡大する状況が続きました。
国民の間では、自民党の従来型政治への不満が高まりました。
終身雇用制度の動揺、フリーターや派遣労働者の増加、就職氷河期など、雇用環境の悪化が社会問題となりました。
小泉政権の改革と影響
「自民党をぶっ壊す」と郵政民営化
2001年に発足した小泉純一郎政権は、「自民党をぶっ壊す」という衝撃的なスローガンを掲げ、従来の自民党政治からの脱却を図りました。
小泉首相は「聖域なき構造改革」を標榜し、既得権益の打破と市場経済原理の導入を推進しました。
最大の政治的成果は郵政民営化でした。
2005年の衆議院選挙では郵政民営化の是非を争点とし、反対する自民党議員には刺客を送るという劇場型政治手法で圧勝しました。
郵政公社の民営化により、340兆円という巨額の資金を民間部門に開放することを目指しました。
小泉政権は他にも道路公団の民営化、特殊法人の整理統合、不良債権処理の加速など、従来の自民党が手をつけられなかった改革を断行しました。
規制緩和とグローバル化への対応
小泉政権は市場原理主義的な政策を積極的に推進しました。
労働者派遣法の改正により製造業への派遣労働を解禁し、労働市場の流動化を図りました。
また、金融機関の不良債権処理を強力に推進し、金融システムの健全化に取り組みました。
対外的には、FTA(自由貿易協定)の推進や外資系企業の参入促進など、グローバル化に対応した政策を展開しました。
企業は国際競争力強化のため、リストラや海外移転を加速させました。
これらの政策により、2002年から2008年まで戦後最長の景気回復「いざなぎ越え景気」を実現しました。
企業収益は大幅に改善し、株価も上昇しました。
格差拡大という副作用
しかし、小泉改革は予期せぬ副作用を生み出しました。
最も深刻だったのは所得格差の拡大です。
正社員と非正規雇用の待遇格差が拡大し、「ワーキングプア」という言葉が生まれました。
地域間格差も拡大しました。
都市部では企業収益の改善により経済が回復した一方、地方では公共事業削減により経済が一層疲弊しました。
三位一体改革による地方交付税の削減も地方経済を直撃しました。
また、社会保障制度の見直しにより、高齢者の医療費負担や介護保険料が増加し、社会的弱者への影響が問題となりました。
「小さな政府」を目指す改革が、セーフティネットの機能低下をもたらした側面もありました。
安倍政権のアベノミクス
「三本の矢」=金融緩和・財政出動・成長戦略
2012年12月に発足した第二次安倍政権は、「アベノミクス」と呼ばれる経済政策を推進しました。
デフレ脱却と経済再生を目指し、「三本の矢」として大胆な金融緩和、機動的な財政出動、民間投資を喚起する成長戦略を掲げました。
第一の矢である金融緩和では、日本銀行に2%のインフレ目標を設定させ、「量的・質的金融緩和」を実施しました。
黒田東彦日銀総裁のもとで、マネタリーベースを2年で2倍にするという異次元の金融緩和が行われました。
第二の矢の財政出動では、「国土強靱化」を掲げて公共投資を拡大し、景気の下支えを図りました。
また、補正予算を積極的に編成し、短期的な景気刺激策を実施しました。
第三の矢の成長戦略では、規制緩和、税制改革、TPP参加、女性活躍推進など、構造改革による潜在成長率の向上を目指しました。
株価と雇用の回復
アベノミクスの効果は比較的早期に現れました。
円安・株高が進行し、日経平均株価は2万円台を回復しました。
企業収益は大幅に改善し、設備投資も増加に転じました。
雇用情勢も大きく改善しました。
有効求人倍率は1.6倍台まで上昇し、完全失業率は3%を下回る水準まで低下しました。
特に女性や高齢者の就業率向上が顕著で、労働力不足が懸念されるほどになりました。
企業の賃上げも進みました。政府は経済界に賃上げを要請する「官製春闘」を展開し、基本給を引き上げるベースアップも復活しました。
消費税率の引き上げにもかかわらず、個人消費は一定の底堅さを維持しました。
成果と限界
アベノミクスは一定の成果を上げましたが、限界も明らかになりました。
最大の課題は2%のインフレ目標の達成でした。
原油価格の下落や消費税増税の影響もあり、物価上昇率は目標を大きく下回って推移しました。
潜在成長率の向上も道半ばでした。
労働生産性の向上や技術革新による成長力強化は期待されたほど進まず、人口減少社会における持続的成長の実現は困難な課題として残りました。
財政健全化も大きな課題でした。
税収は増加しましたが、社会保障費の自然増により財政赤字の根本的改善には至りませんでした。国債残高の対GDP比は依然として高水準で推移しました。
また、格差問題も完全には解決されませんでした。
株価上昇や企業収益改善の恩恵は主に高所得者層に帰属し、中間層以下の実質所得向上は限定的でした。
まとめ
戦後から現在まで、自民党は経済成長と国民生活の安定を最重要課題として政策運営を行ってきました。
池田勇人の所得倍増計画に始まり、田中角栄の日本列島改造論、小泉純一郎の構造改革、安倍晋三のアベノミクスまで、時代の変化に応じて経済政策を転換させながら、日本経済の舵取りを担ってきました。
高度経済成長期には「官民協調」による成長モデルで大きな成功を収め、日本を世界第2位の経済大国に押し上げました。
バブル崩壊後の長期停滞期には試行錯誤を重ね、小泉改革では市場原理の導入による構造転換を図りました。
そして、アベノミクスでは金融政策と成長戦略を組み合わせた包括的な経済政策を展開しました。
これらの政策には成功と失敗の両面がありますが、自民党が一貫して日本経済の方向性を大きく決定づけてきたことは間違いありません。
経済成長重視の政策は国民生活の向上に大きく貢献した一方で、格差拡大や環境問題、財政赤字といった課題も生み出しました。
今後、日本は人口減少と超高齢化という人類史上経験したことのない課題に直面します。
労働力人口の減少、社会保障費の増加、地方の過疎化など、従来の成長モデルでは対応困難な問題が山積しています。
自民党には、デジタル化やイノベーションの推進、生産性向上、持続可能な社会保障制度の構築など、新たな政策パラダイムの構築が求められています。
経済政策を軸に戦後日本を牽引してきた自民党が、これからの時代にどのような成長戦略を描くかが、日本の未来を左右する重要な要素となるでしょう。
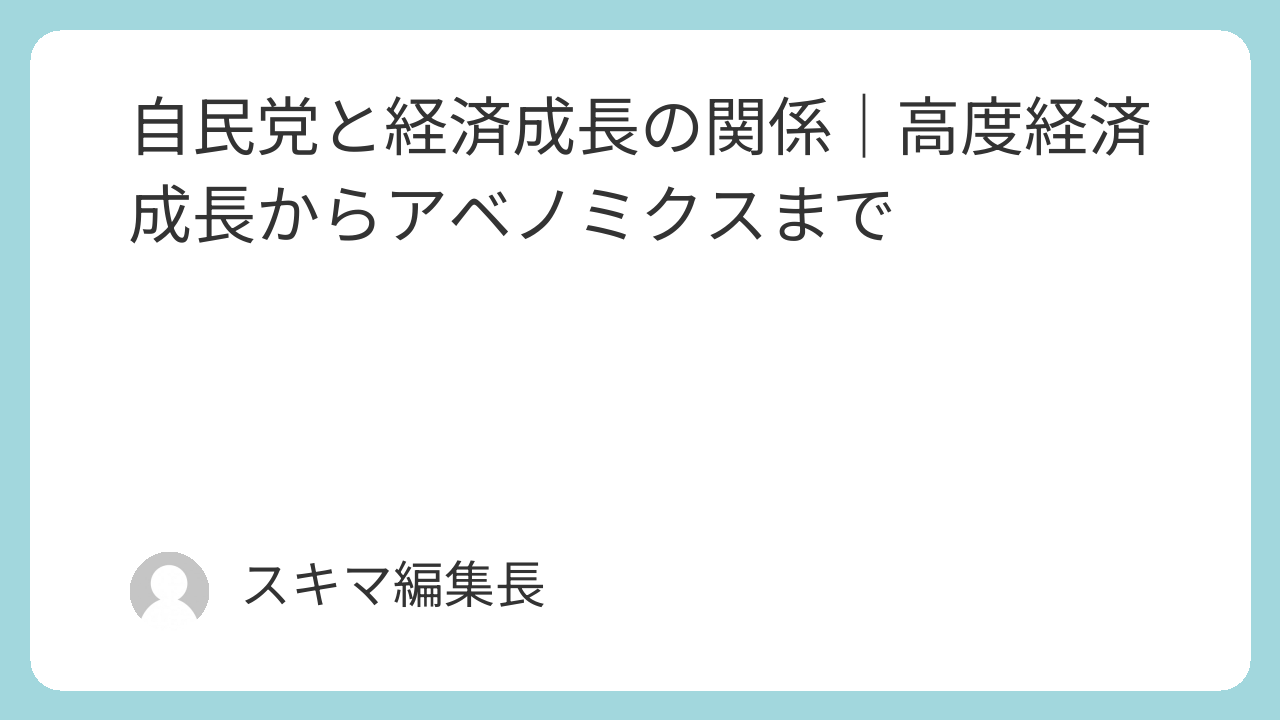
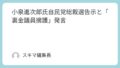

コメント