2025年10月20日、Amazonのクラウドサービス「AWS(Amazon Web Services)」で、
世界規模の大規模障害が発生しました。
SNS、ゲーム、決済アプリ、さらには公共機関のシステムまでもが一時的に停止し、
“インターネットの心臓”ともいえるクラウドの脆弱性が浮き彫りになりました。
本記事では、海外メディアが報じた内容をもとに、
障害の概要・原因・影響範囲、そして今後の課題を整理します。


AWSのシステム障害の概要

2025年10月20日、世界中の多くのウェブサービスでアクセス障害が発生しました。
原因は、Amazonが提供するクラウドサービス「AWS(Amazon Web Services)」の大規模なシステム障害。
障害は主に米国東部のデータセンター(US-East-1リージョン)で発生し、
約3時間にわたって多くのサービスが停止または遅延しました。
AWSは、企業や政府機関、スタートアップまで幅広く利用されているクラウド基盤です。
Webサイトやアプリのサーバー、データベース、AI処理など、
現代のインターネットを支える“裏方”の存在とも言えます。
そのため、AWSで障害が発生すると、
直接AWSを契約していない企業や個人ユーザーにも影響が広がることが特徴です。
AWS公式は「一部のサービスでエラー率や遅延が増加している」と発表。
数時間後には回復の兆候を示しましたが、
社会的な影響の大きさから、各国メディアが一斉に報じる事態となりました。
影響を受けた主なサービス
今回の障害によって影響を受けたのは、実に多岐にわたります。
SNSでは Snapchat や Signal などが一時的に利用不能となり、
オンラインゲームの Roblox や Fortniteなどもアクセスが途絶。
さらに、語学学習アプリの Duolingo や、米国の決済アプリ Venmo など、
日常生活に密着したサービスにも影響が及びました。
また、一部の銀行や政府関連サイト、通信会社のシステムにも障害が確認され、
業務や行政サービスが一時的に遅延するケースも見られました。
SNS上では「メッセージが送れない」「アプリが開かない」といった報告が相次ぎ、
クラウドサービスの停止が社会全体に与える影響の大きさを改めて実感させる出来事となりました。
AWSの障害の原因

今回の障害について、ロイターやガーディアンの報道では、
外部からのサイバー攻撃ではなく、AWS内部のシステムトラブルが原因とされています。
特に、ネットワークを最適化する「ロードバランサー」と呼ばれる仕組みの監視サブシステムに
不具合が発生したことが引き金となった可能性が高いとみられています。
この部分が正常に動作しなかったことで、サーバー間の通信が乱れ、
多くのサービスが同時にエラーを起こしたと分析されています。
AWSは発表の中で、「根本原因を特定し、再発防止策を実施している」と説明していますが、
詳細な技術的背景については、今後の公式報告を待つ必要があります。
サイバー攻撃では無いと発表されているため、アスクルやアサヒビールなどのように個人情報が外部に漏れているということはないと思われます。


浮き彫りになった「クラウド依存のリスク」
今回の障害で最も注目されたのは、クラウドへの依存度の高さです。
現代社会では、銀行のオンラインシステム、医療機関のデータベース、
行政サービス、通信ネットワークなど、あらゆる分野でクラウドが利用されています。
日本のマイナンバーのシステムもAWSのクラウドが使用されていると聞きます。
※マイナンバーの情報をAmazonが管理しているということではありません。
AWS、Google Cloud、Microsoft Azureの3社だけで、世界のクラウド市場の6割以上を占めており、
まさに「インターネットの中枢」とも言える存在です。
このようにインフラが少数の企業に集中していることで、
一社の障害が広範囲に波及する“単一障害点(Single Point of Failure)”のリスクが生まれます。
実際、英国政府は今回の事態を受けて、
AWSを「重要な第三者(critical third party)」として金融セクターの監督対象に加える動きを見せています。
便利で効率的なクラウドサービスは、社会全体を支える一方で、
その裏には「依存」というリスクが存在する――。
このバランスをどう取るかが、今後の課題となりそうです。
今回のAWS障害を受け、専門家たちは次のような対策の必要性を指摘しています。
今後の課題と対策
① マルチクラウド戦略の推進
企業が複数のクラウドサービスを併用することで、
一方がダウンしても他方で代替処理ができるようにする仕組みです。
コストは増えますが、信頼性を高めるためには有効な選択肢です。
② 政府・企業によるリスク評価体制の強化
公共サービスや重要インフラにおいては、
障害発生時の影響シミュレーションやバックアップ体制を定期的に検証することが不可欠です。
③ 障害情報の透明性と共有
AWSをはじめとするクラウド事業者は、障害の原因や対応状況を
より迅速かつ透明性を持って発信することが求められます。
利用者が「何が起きているのか」を把握できるだけでも、混乱は大きく減ります。
まとめ:便利さの裏に潜むリスク
今回のAWS障害は、一時的なトラブルで終息しました。
しかし、私たちが日常的に利用しているアプリやサービスの多くが、
たった数社のクラウド企業の上で成り立っているという事実は、
非常に大きな示唆を与えています。
クラウドは、もはや「便利なインフラ」ではなく「社会の生命線」。
だからこそ、その安全性や分散性について、
ユーザー一人ひとりも意識を持つ時代に来ているのかもしれません。
デジタルの恩恵を享受しながらも、
その裏にある“見えないリスク”に目を向けること——。
それが、これからのテクノロジー社会を生きる上で欠かせない姿勢です。
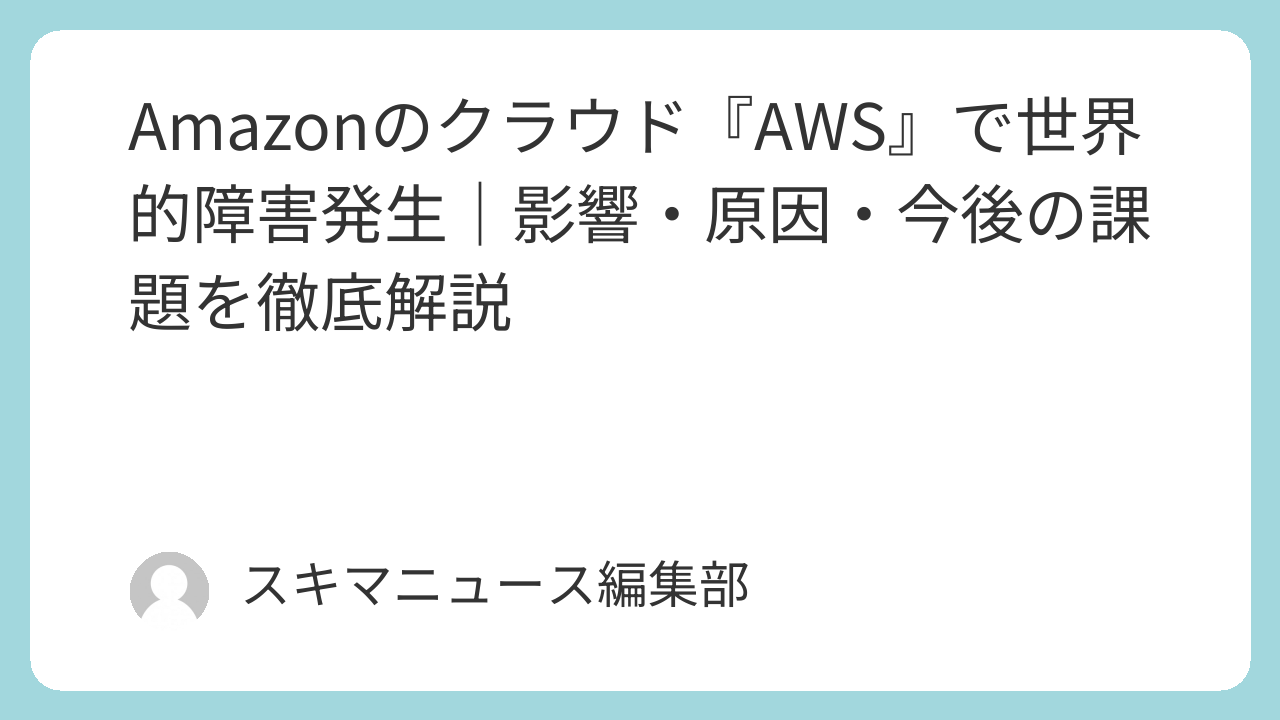
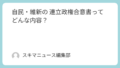

コメント