2023年4月、日本の子ども政策に新たな時代が幕を開けました。
こども家庭庁の発足です。
深刻化する少子化、増加し続ける児童虐待、国際比較で最下位となった若者の自己肯定感。
これらの課題に対し、従来の省庁の枠を超えて一元的に取り組む「司令塔」として、大きな期待を背負ってスタート『こども家庭庁』しました。
しかし、発足から2年半が経過した2025年10月現在、その評価は大きく分かれています。
児童手当の拡充や妊婦支援の充実など具体的な成果がある一方で、
SNS上では「予算の無駄遣い」「効果が見えない」といった厳しい批判も相次いでいます。
本記事では、こども家庭庁の設立に至る歴史的背景を振り返り、現在までの取り組みと直面している課題を、客観的なデータと世論の声を交えながら検証していきます。
設立の背景:なぜ「こども家庭庁」が必要だったのか

縦割り行政の限界
こども家庭庁の設立を後押しした最大の要因は、従来の縦割り行政の限界でした。
子どもに関する政策は、内閣府、厚生労働省、文部科学省、警察庁など複数の省庁に分散しており、総合的かつ迅速な対応が困難でした。
例えば、児童虐待の対応では厚生労働省が中心となる一方、学校でのいじめ問題は文部科学省の管轄。
子どもの貧困対策も複数の省庁にまたがり、政策の隙間に落ちる子どもたちが存在していました。
深刻化する社会課題
設立の背景には、以下のような深刻な社会課題がありました。
- 少子化の加速
- 児童虐待の増加
- 子供の肯定感の低さ
- 子供の貧困
問題1:少子化の加速
子供の出生率は年々減少し、2024年は68万6061人と過去最小を更新しました。
また、合計特殊出生率は1.1.5台まで低下しています。
これは、少子化の加速は、厚生労働省が予測するペースと比べて、早く進行しています。
このペースで少子化が続けば、社会保障制度の30年後には維持が困難になることが予測されます。
問題2: 児童虐待の増加
児童相談所への虐待相談件数は2025年度の長さによれば 22万5,509件を突破と年々増加しています。
虐待による子どもの死亡事例も後を絶たない状況になっています。
子どもの自己肯定感の低さ
国際調査によれば、日本の若者で『自分に満足している』と答えた人は全体の4割という調査結果もでています。
これは、米国が8割なことを考えると低いということがわかります。
また、15〜19歳の死因トップが自殺という深刻な状況でもあります。
他にも不登校児童生徒数も年々増加しており、2025年の調査結果によれば、34万6000人と過去最多の数値を出しています。
子どもの貧困
こどもの8.7人に1人の子どもが相対的貧困状態にあると言われており、
親の低収入、非正規雇用の増加、ひとり親世帯の増加が主な原因とされいます。
この経済格差が、経済格差が教育格差に直結する構造といえます。
これらの課題に対し、1994年に批准した子どもの権利条約の理念を実現し、子どもの最善の利益を第一に考える行政組織の必要性が長年指摘されてきました。
そういった背景から『こども家庭庁』が誕生するきっかけとなったと言えます。
政治的議論の高まり
実は「子ども省」の構想自体は新しいものではありませんでした。
2011年頃、民主党政権下で「子ども家庭省」の設置が議論されましたが、政権交代などもあり実現には至りませんでした。
転機となったのは2018年の成育基本法の成立です。
この法律の附則で「子どもの健やかな成育のための行政組織の在り方を検討する」ことが明記され、法的根拠が整いました。
2021年、菅義偉首相が「こども庁」創設への意欲を示したことで議論が本格化。
少子化対策と子どもの権利保護を両輪とする新組織の設立に向けて、政治が大きく動き出したのです。
設立までの道のり:構想から発足まで

2021年:検討と議論の年
1月〜6月:政府方針の決定
2021年1月、自民党の有志議員グループが「こども庁」創設を提言。
これを受けて菅首相が参議院決算委員会で創設に意欲を示しました。
同年6月の「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)」には、「新たな行政組織の創設の検討に着手」と明記され、政府の正式方針となりました。
9月〜12月:組織設計と名称変更
9月に「こども政策の推進に係る有識者会議」が設置され、専門家による議論がスタート。
当初は「こども庁」という名称でしたが、
自民党内の保守派や公明党から「家庭の役割を重視すべき」との意見が強く出され、
12月に「こども家庭庁」へと名称が変更されました。
この名称変更は、子どもの権利を重視する立場と、家族単位での支援を重視する立場の妥協点として位置づけられましたが、一部からは「子ども中心という理念が後退した」との批判も受けました。
2022年:法案成立の年
2月:法案提出
2月25日、こども家庭庁設置法案が閣議決定され、国会に提出されました。
法案には以下の主要な柱が含まれていました。
- 内閣府の外局として設置
- 定員約400名規模
- 厚生労働省のこども家庭局、内閣府の子ども・子育て本部を移管
- 予算規模は約4兆円(初年度)
- 子ども政策の司令塔機能を担う
6月:国会での可決・成立
国会審議では、組織の権限や予算の妥当性、文部科学省との役割分担などについて活発な議論が交わされました。
最終的に6月15日に参議院本会議で可決・成立。
同月22日に公布され、2023年4月1日の施行が決定しました。
準備期間:組織立ち上げへ
法案成立後は、実際の組織立ち上げに向けた準備が本格化しました。
- 職員の配置転換と新規採用
- 関係省庁からの業務移管の調整
- 予算・会計システムの構築
- 地方自治体との連携体制の整備
特に難航したのが、文部科学省との役割分担でした。
いじめ問題や不登校対策など、学校教育と密接に関わる分野については
両省庁の綿密な調整が必要とされました。
こども家庭庁の発足
組織構成と体制
2023年4月1日、こども家庭庁が正式に発足しました。
初代長官には渡辺由美子氏が就任。
組織は以下の3部門で構成されました。
企画立案・総合調整部門
- こども家庭庁全体の企画立案
- 各省庁との総合調整
- こども大綱の策定
成育部門
- 妊娠・出産支援
- 母子保健
- こども誰でも通園制度
- 保育・幼児教育
支援部門
- 児童虐待防止対策
- 社会的養護
- ひとり親家庭支援
- 障害児支援
- いじめ防止対策(文科省と連携)
初年度の職員数は約465名、予算規模は約4兆円でスタートしました。
設立時の理念と目標
こども家庭庁は「こどもまんなか社会」の実現を掲げ、以下の基本理念を打ち出しました。
- こどもの視点に立った政策立案
- 当事者であるこどもの意見を政策に反映
- 「こども若者★いけんぷらす」という意見聴取の仕組みを構築
- 切れ目のない支援
- 妊娠前から社会に出るまで一貫した支援
- ライフステージに応じた縦断的な政策
- データに基づく政策立案(EBPM)
- こどもの実態を正確に把握
- 効果測定と政策改善のサイクル確立
発足後の主な取り組み
2023年度:基盤整備の年
こども大綱の策定
2023年12月、政府として初めて「こども大綱」を閣議決定しました。これは子どもの権利条約の理念に基づき、今後5年間の子ども政策の方向性を示す重要な文書です。
大綱では、すべてのこどもが幸せに暮らせる社会の実現に向けて、6つの基本理念と具体的な数値目標を設定。
- こどもの視点、子育て当事者の視点に立った政策立案
- 全てのこどもの健やかな成長、Well-being※の向上
- 誰一人取り残さず、抜け落ちることのない支援
- こどもや家庭が抱える様々な複合する課題に対し、制度や組織による縦割りの壁、年度の壁、年齢の壁を克服した切れ目のない包括的な支援
- 待ちの支援から、予防的な関わりを強化するとともに、必要なこども・家庭に支援が確実に届くプッシュ型支援、アウトリーチ型支援に転換
- データ・統計を活用したエビデンスに基づく政策立案、PDCAサイクル(評価・改善)
「こども大綱」に基づく幅広いこども政策の具体的な取組を一元的に示したアクションプランとして「こどもまんなか実行計画」を取りまとめ、今後毎年改定し、継続的に施策の点検と見直しを図ることとされました。
こども未来戦略の始動
政府は「異次元の少子化対策」として、以下の3つの柱から成る「こども未来戦略」を策定しました。
- 子育て世帯の家計を応援
- すべてのこどもと子育てを応援
- 共働き・共育てを応援
2024年度:政策の本格実施
児童手当の大幅拡充
2024年10月から所得制限が完全撤廃され、年収1200万円でもOKになりました。
これにより、より多くの家庭が支援を受けられるようになりました。
支給額は0〜3歳未満が月1万5000円、3歳〜中学生が月1万円。
さらに第3子以降は月3万円に増額され、多子世帯への手厚い支援が実現しました。
妊娠・出産支援の強化
妊婦のための支援給付や妊婦等包括相談支援事業が開始され、妊娠期から切れ目のない支援体制が整備されました。
産後ケア事業も全国展開が進み、産後うつの予防や育児不安の軽減に貢献しています。
こども誰でも通園制度の試行
保育所等を利用していない家庭でも、定期的に保育サービスを利用できる
「こども誰でも通園制度」の試行が始まりました。
孤立しがちな在宅育児家庭への支援として注目されています。
2025年度:加速化プランの展開
2025年度から本格実施する主な内容として、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金の創設が行われています。
予算規模も大幅に拡充され、子ども・子育て関連予算は7兆円規模に達しています。
「こどもまんなか実行計画2025」では、さらに踏み込んだ施策の展開が示されています。
しかし、そんな子供や子育て支援をしているこども家庭庁ですが、世間では批判的な意見が多数みうけられます。
なぜなのでしょうか?
その理由をご紹介します。
こども家庭庁関連の問題
こども家庭庁はしっかりとした目標を掲げながらも以下のような問題を起こしてきました。
- ベビーシッター券の“乱発”・金銭・パワハラ疑惑
女性PRIMEやSNSでも話題になった事件で70万枚のパーティ券から裏金をつくったという事件です。 - ベビーライフ事件
民間の特別養子縁組あっせん団体「ベビーライフ」が事業を停止し、2012~2018年度の間に約300人の子どもがあっせんされたうち、半数以上の受入れ親が外国籍だったことが明らかになった事件。 - 虐待判定 AI の失敗・導入見送り
児童虐待の疑い判定に活用するAI(人工知能)システムの導入が10億円規模で進められましたが、試験導入で判定と現場の判断のズレが大きく、2024年度の全国導入が見送られました。
といった事件がありました。
他にもSNSでは、
「6.4兆円の使途不明金」「中抜き利権」「裏金作り」などと称する動画やSNS投稿があり、
こども家庭庁を「闇」「不正の温床」と扱っているものがあります。
直面している課題と批判
SNS上での批判の声
こども家庭庁に対しては、発足当初から様々な批判が寄せられています。
「効果が見えない」という声
「こども家庭庁を廃止すると勤労者1人につき年間107,000円の減税ができる」という情報がネットで拡散されたことから、「こども家庭庁を廃止したほうがいい」という声がSNSなどで高まる結果となりました。
特に指摘されているのは以下の点です。
- 出生率の改善が見られない
- 子どもの自殺率が減少していない
- 不登校児童数が増加し続けている
- 児童虐待件数も減少していない
これらの指標が改善していないことから、
「7兆円以上の高額な予算を使っているのに成果が出ていない」という批判が根強くあります。
施策の方向性への疑問
商業施設などで妊婦や子ども連れを優先する「こどもファスト・トラック」、Jリーグとのコラボやタレントを招いたイベント、子育て中の家庭を若者が訪問する「家族留学」への支援、「家族の日」写真コンクール主催といった施策を発表するたびに、ネット上は大炎上する騒ぎになっている状況です。
これらの施策は広報・啓発活動の一環ですが、
「本質的な問題解決につながらない」
「予算の使い方が間違っている」
という批判を受けています。
AI虐待判定システムの失敗
10億円かけた虐待判定AIのミスが非常に多いことで導入を見送ったことも、予算の無駄遣いとして批判されています。
組織的な課題
権限の限界
こども家庭庁は「司令塔」と位置づけられていますが、実際には文部科学省の所管する学校教育分野など、直接的な権限が及ばない領域が多く存在します。
「不登校児童への対応」や「学校でのいじめ」への対応が難しいのが現状です。
縦割り行政を打破するという目標に対して、組織的な限界があるとの指摘があります。
地方との連携不足
子ども政策の多くは地方自治体が実施主体となりますが、こども家庭庁と自治体との連携体制が十分に構築されていないという課題も浮上しています。
実際に、地方の会社では育休制度を男性が取ると減給の対象となる企業もまだまだ存在しています。
財源の問題
予算規模は大きいものの、その大部分は既存の施策の継続に充てられており、新規の施策に回せる予算は限定的です。
また、少子化対策の財源として導入される「子ども・子育て支援金」については、国民負担の増加を懸念する声もあります。
実際の成果はあるのか
批判が多い一方で、具体的な成果も出始めています。
ポジティブな側面
貧困家庭に月2万円支給されているという背景があり、支給を必要としている人からは廃止に反対する声が上がっています。
経済的に困窮する家庭への支援は確実に届いています。
また、児童手当の所得制限撤廃により、子育て世帯の経済的負担が軽減されたことは評価できます。
妊娠期からの伴走型支援も、孤立を防ぐ効果が期待されています。
まだ時間が必要
ただし、少子化や児童虐待といった社会課題は、一朝一夕に解決できるものではありません。
政策の効果が数値として表れるには、数年単位の時間が必要です。
発足から2年半という期間で、抜本的な改善を求めるのは現実的ではないかもしれません。
重要なのは、定期的に政策を検証し、効果が出ていない施策は見直していく姿勢です。
2025年の現状と今後の展望
現在の体制と予算
2025年10月時点で、こども家庭庁の予算規模は約7.3兆円に達しています。
2023年度の4兆円から大幅に増額されており、政府の本気度がうかがえます。
現在の大臣は三原じゅん子氏が務めており、こどもの貧困対策や児童虐待防止対策の推進に力を入れています。
今後の重点課題
透明性の向上
予算の使途について、より詳細な情報公開が求められています。
どの施策にいくら使われ、どのような効果があったのかを明確にすることで、国民の理解を得る必要があります。
効果測定の徹底
政策のPDCAサイクルを確立し、効果が薄い施策は大胆に見直す勇気が必要です。
限られた財源を最大限有効活用するためには、エビデンスに基づく政策立案(EBPM)の徹底が不可欠です。
権限の強化
真の「司令塔」として機能するためには、他省庁への勧告権限の強化など、組織的な権限の見直しも検討課題となるでしょう。
地方との連携深化
自治体の現場で実際に子ども支援を担う職員との連携を強化し、現場の声を政策に反映させる仕組みづくりが重要です。
まとめ:期待と現実の狭間で
こども家庭庁の設立は、日本の子ども政策における歴史的な転換点でした。
長年の課題だった縦割り行政の打破に向けて、ようやく一歩を踏み出したことは評価に値します。
しかし、組織を作っただけでは問題は解決しません。
発足から2年半が経過し、具体的な成果が問われる段階に入っています。
批判の声に真摯に耳を傾けながら、本当に効果のある施策に予算を集中投下していく。
そして何より、子どもたち自身の声を政策に反映させる姿勢を貫くことが、こども家庭庁に求められています。
少子化、児童虐待、子どもの貧困。これらの課題は一つの組織だけで解決できるものではありません。
政府、自治体、企業、地域社会、そして私たち一人ひとりが「こどもまんなか」の意識を持って取り組むことが、真の解決につながるはずです。
こども家庭庁の今後の歩みを、私たちは注視し続ける必要があります。
批判すべき点は批判し、評価すべき点は評価する。
そうした健全な監視の目があってこそ、この組織は本当の意味で機能していくのではないでしょうか。
参考情報
- こども家庭庁公式サイト:https://www.cfa.go.jp/
- こども未来戦略:https://www.cfa.go.jp/resources/kodomo-mirai
- こどもまんなか実行計画2025
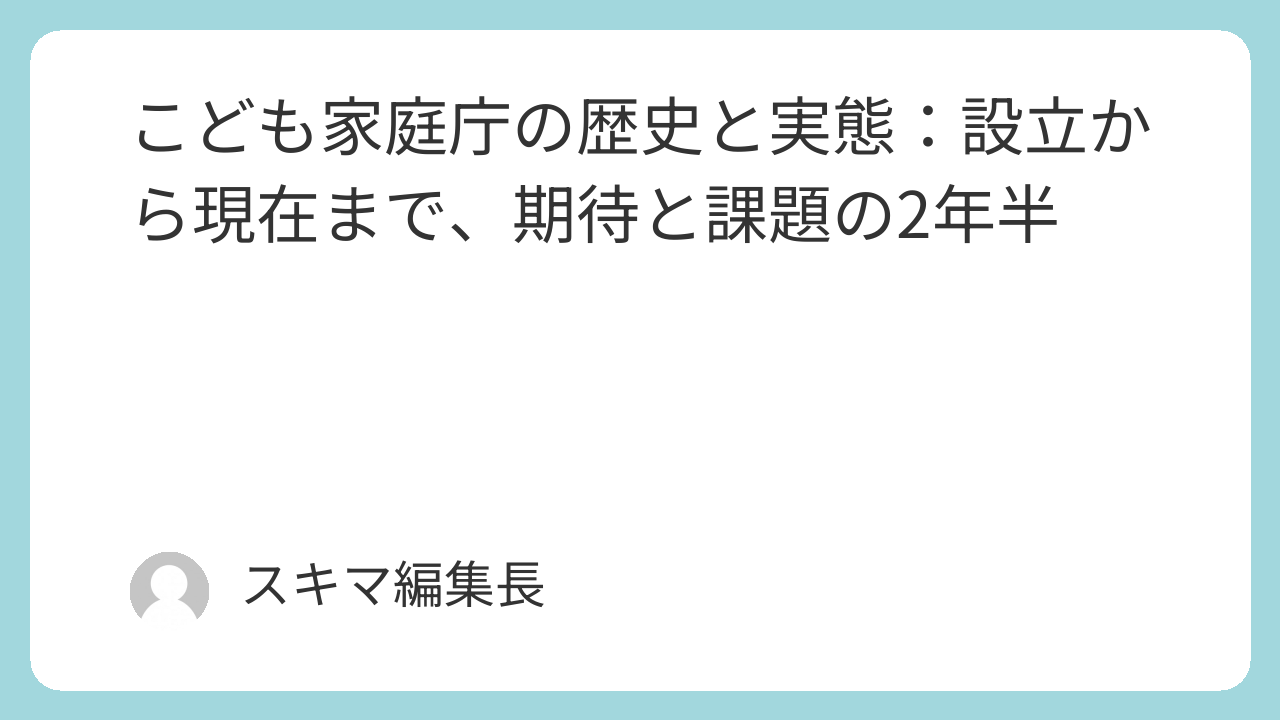
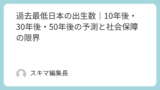
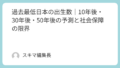
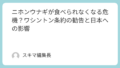
コメント